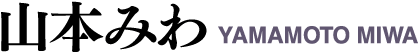2025年3月18に開かれた茨城県議会予算特別委員会に、公明党代表して山本美和議員が質問に立ちました。
山本議員は、不登校対策として「メタバース教室」の導入を提案しました。県教育長は導入を具体的に検討する姿勢を明らかにしました。
メタバース教室導入のメリットと課題
近年、不登校の児童生徒が増加する中で、その対策としてメタバース教室の導入が注目されています。ICT技術の進展により、従来の教室に代わる新しい学びの場として、仮想空間を利用した教育手法が現実味を帯びてきました。特に、学校という物理的な空間に通うことに心理的な抵抗を感じる子どもたちにとって、メタバース教室は新たな希望となり得ます。自宅からインターネットを介して接続できるため、安心して授業に参加することができ、また自分自身をアバターで表現することによって、他人の視線や評価への不安が軽減される効果もあります。
さらに、メタバース内では全国の同じような境遇の子どもたちと出会い、バーチャルな空間で自然なコミュニケーションを取ることが可能となります。これにより、孤立感の解消や自己肯定感の向上にもつながりやすく、教員や支援スタッフとの交流を通じて、徐々に対人関係に慣れていくことも期待されます。また、個別の学習進度や関心に応じて教材を提供することができるため、画一的な授業に比べてより柔軟で効果的な学びが実現可能となります。時間や場所にとらわれず、子どものリズムに合わせた学習支援ができる点は、従来の教育にはない大きな強みと言えるでしょう。
しかしながら、こうしたメタバース教室にも課題は少なくありません。まず第一に、長時間にわたってディスプレイを見ることによる健康被害、特に視力の低下や身体の不調などが懸念されます。また、仮想空間に没入することによって、身体を動かす機会が減少し、運動不足になる可能性も指摘されています。さらに、バーチャル上での人間関係と現実世界での対人スキルは必ずしも一致するものではなく、現実の社会生活に必要なコミュニケーション能力や感情の機微を学ぶ機会が不足する恐れもあります。
加えて、すべての家庭がメタバース教室を利用できるわけではありません。パソコンやインターネット環境、場合によってはVR機器といった一定の設備が必要となるため、経済的な格差がそのまま教育格差につながってしまう可能性も否定できません。また、教育現場においても、教職員がこうした新しい技術を活用できるだけのICTリテラシーを持っているとは限らず、導入には相応の研修や体制整備が必要です。メタバースを活用した指導法には、子どもたち一人ひとりの心の状態を丁寧に把握し、適切に対応するための専門的な支援も欠かせません。
総じて言えることは、メタバース教室は不登校という複雑かつ個別性の高い問題に対する有効なアプローチの一つであるという点です。しかし、それは万能の解決策ではなく、あくまでも選択肢の一つに過ぎません。現実の学校生活とのバランスを取りながら、子どもたちがそれぞれのペースで社会との接点を回復し、自立した未来へと歩んでいけるよう、多様な教育の在り方を模索することが求められています。メタバース教室の導入は、その一歩に過ぎませんが、技術と教育の融合によって、新たな可能性が開かれることは間違いありません。