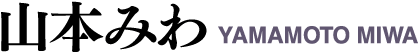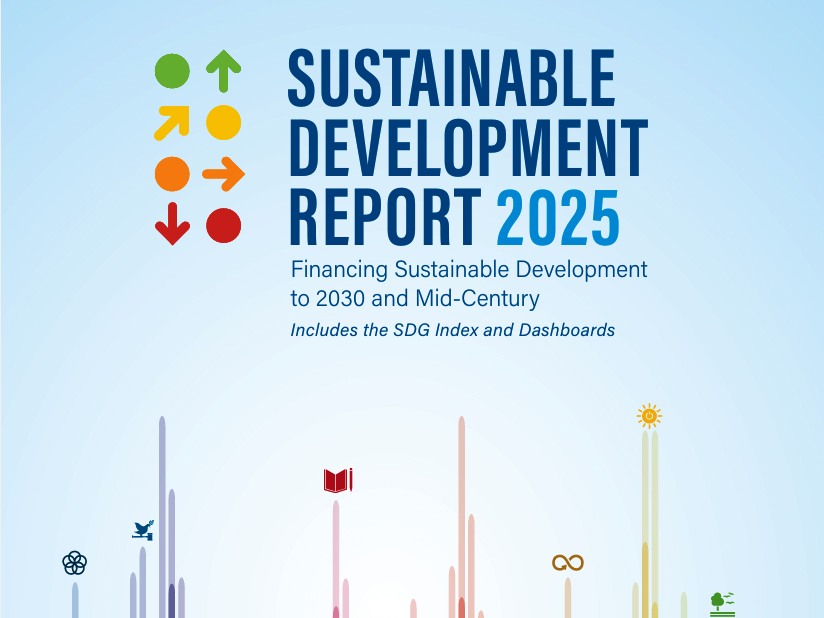
7月29日に発表された「持続可能な開発報告書2025」によれば、日本のSDGs達成度は世界167カ国中19位となり、欧州以外で唯一トップ20に入りました。保健や教育分野で高く評価された結果ですが、これで「日本は安心」と受け止めるのは危険です。なぜなら、このランキングの陰に、深刻な課題が隠れているからです。
報告書では、日本は気候変動対策、持続可能な消費、生物多様性の保全、そしてジェンダー平等の分野で「深刻な課題あり」と指摘されました。特にジェンダーギャップは、日本が国際社会から最も厳しい評価を受けている分野です。G7の中では最下位、世界全体でも依然として低い水準にとどまっています。

なぜ日本はここまで遅れているのか。その背景には、社会に根強く残る「構造的慣性」があります。経済やインフラといった“ハード”の分野では力を発揮できても、人権や平等、自由といった“ソフト”の分野では改革が進みにくい。女性が政治や経済の場で参画することへの制度的・文化的な壁がいまだ高く、結果として意思決定の場で女性の声が十分に反映されない現実があります。
茨城県議会も例外ではありません。2024年時点で女性議員の比率はわずか10%。人口の半分が女性であるにもかかわらず、この数字は非常に低い水準です。私は女性議員の一人として、この不均衡を変えていく責任を強く感じています。意思決定の場に女性が加わることで、子育て支援や介護、教育、働き方改革など、生活に直結する課題がより実効性を持って政策に反映されるのです。
今回の報告書は、茨城に住む私たちにとっても大切なメッセージを投げかけています。県政においては、環境政策の強化と並行して、ジェンダー平等を「特別なテーマ」ではなく「社会の根幹」と位置付け、制度改革を進める必要があります。たとえば、女性の政治参画を拡大するための支援制度、企業や行政における管理職・意思決定層への登用促進、働き方や育児・介護を男女がともに担える環境整備などです。
SDGsは「誰一人取り残さない」ことを理念としています。ジェンダー平等の遅れを克服することは、その理念を現実のものとするために避けて通れません。茨城から声を上げ、行動を積み重ねていくことが、日本全体の変革へとつながると信じています。私も議会の中で引き続き、ジェンダー平等と持続可能な未来の実現に向けて全力を尽くしてまいります。