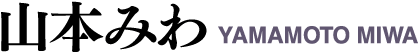10月7日、県議会公明党の山本美和議員は、県議会の一般質問で「つくば科学技術特区(つくば国際戦略総合特区)」について質問を行いました。
この特区は、2011年に国の指定を受けてスタートしたもので、つくば市や東海村を中心に、最先端の科学技術研究の成果を社会に実装し、新しい産業を生み出すことを目的としています。これまでの取り組みを振り返ると、研究の街・つくばならではの成果が数多く生まれています。
大井川知事からは、生活支援ロボットの安全基準の確立や、ゲノム編集による「GABA高蓄積トマト」の世界初の販売など、世界に先駆けた成果があったとの答弁がありました。たしかに、研究の成果が実際に社会に広がり始めていることは、大きな前進だと思います。
一方で、特区の大きな柱である「規制緩和の特例措置」が1件にとどまったことも指摘され、制度としての限界や課題も明らかになりました。知事も「規制緩和の面での成果は少なかった」と率直に述べられました。
特に気になったのは、こうした特区の成果が県民の皆さんに十分に伝わっていないことです。つくばで何が生まれ、どんな新しい技術が生活に役立とうとしているのか、その実感が届きにくい状況があります。山本議員は、もっとわかりやすく県民に伝える工夫が必要だと質問しました。
知事からは、「地域で実感できるメリットが乏しかったため、県民の理解が十分ではなかった」との答弁があり、今後は国に対してより実効性のある制度づくりを求めるとともに、革新的スタートアップの育成や新産業の創出など、成果を積極的に発信していく考えが示されました。

特区の中では、次世代がん治療「BNCT(ホウ素中性子捕捉療法)」が、2023年度から初発の悪性脳腫瘍を対象とした治験を開始しています。県は「いばらき量子ビーム研究センター」で治験の環境を整え、国の資金確保を支援するなど、実用化に向けた取り組みを続けています。さらに、藻類バイオマス研究では、化粧品開発に加え、航空燃料(SAF)への応用に向けた研究も進んでおり、つくば発の未来産業の芽が着実に育っています。
この特区は2025年度で終了しますが、ここで培われた研究設備や人材、ネットワークは、茨城県の大切な財産です。これからは、制度の枠を超え、つくば全体を「イノベーションの現場」として発展させていくことが求められます。
山本議員は、つくばが“研究のまち”から“実装のまち”へと進化していくことを強く願っています。科学技術の成果を県民の暮らしの中で実感できるようにすること――それこそが、この特区が残した最大の使命だと感じています。
これからも県民の皆さまに寄り添いながら、つくばの可能性を未来につなげるため、しっかりと取り組んでまいります。