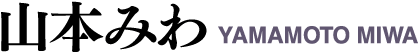令和6年度の茨城県におけるふるさと納税実績がまとまりました。県全体の総受入額は約391億円と前年を上回りましたが、寄付件数は減少し、一件あたりの平均寄付額が上昇しているのが特徴です。全国的にも高額な返礼品や体験型返礼品が注目され、高所得層を中心に関心が集まっていることが背景にあります。
県内で見ますと、守谷市が70億円超でトップ、境町が60億円、日立市が約32億円と続きました。その一方で、返礼品の供給難に直面した境町では寄付額が減少するなど、特定の返礼品に依存するリスクも浮き彫りになっています。
私の地元・つくば市の実績は約2億7,400万円、前年の140%と大きく伸びました。これは嬉しい成果ではありますが、県内他市と比較するとまだ改善の余地が大きいのも事実です。つくば市は、世界的な研究学園都市としての知名度や、多彩な農産物・加工品といった地域資源を持ちながら、その魅力を十分にふるさと納税に結び付け切れていないと感じています。
例えば、科学のまちならではの「研究施設見学」や「最先端技術を体験できるプログラム」、また豊かな自然を活かした「農業体験」「里山散策」「教育型ワークショップ」など、地域性を反映した体験型返礼品の可能性は大きいと考えます。全国では、横浜市が鉄道の運転体験を返礼品にしたり、高知県四万十町がカヌー体験を提供するなど、ユニークな発想で関係人口を広げる取り組みが広がっています。つくば市も同様に、「つくばならでは」を返礼品に込めることで、一過性の寄付ではなく、地域への継続的な関わりにつなげられるでしょう。
さらに重要なのは、返礼品の魅力だけではなく、その背景にあるストーリーをしっかりと伝えることです。食や特産品だけでなく、「この寄付が子どもの教育や地域の環境保全にどう役立つのか」を明確に示すことが、寄付者の共感を呼び、長期的な信頼関係を育てます。
来年10月には制度改正も予定され、返礼品は地場産品に限られ、調達費用の上限や宣伝方法も一層厳格化されます。これからは「お得だから寄付する」のではなく、「地域を応援したいから寄付する」という本来の姿へと転換していくことが求められています。
つくば市には、科学・教育・自然という唯一無二の魅力があります。これをふるさと納税にどう活かし、地域の持続可能な発展につなげていくかが大きな課題であり、同時に大きな可能性です。私は県議会の一員として、この仕組みを地方創生の力に変えていけるよう、引き続き取り組んでまいります。